2014年04月26日
水換え?足し水? 3話 2通り
水換えしても矛盾して困っている からの続きです。
ここからは状況によって枝分かれします。
それは地域によって水換えに使う「水」そのものが違うからです。
それと、自然に「わく」バクテリアの種類とバランスも違うからです。
例えば当店(富士市蓼原)の水道水の「水」は日によってバラつきはありますが、
リン酸値1リットル当たり1.0~2.0mg、硝酸値1リットル当たり30~40mg
ついでに珪酸値1リットル当たり10~50mg以上(多すぎて計測不可能な日もありました)
それなのにPHは8.0~8.5
余談ですが、この3種類はそれぞれ、緑ゴケ、黒ひげゴケ、茶ゴケの主栄養素です。
これらを減らしたいのに水を換えれば換えるほどコケは元気になってしまいます。

このような富士市の水は矛盾以前の問題ですが、水替えに使う水にリン酸、硝酸が無いという事が前提で、部分換水をしている場合は
徐々に水換えの量を増やしたり、水換えの周期を早めたりします。それでも常に悪化していく為、定期的な全換水をする必要があり、(ほぼリセット状態)
その全換水までの時間稼ぎの手段として普段の部分換水がある訳です。
フィルターはなるべく洗わず、とにかく水換えという方法。
この考えは、自然に「わく」バクテリアが硝酸に変化させる好気性の酸化細菌メインの場合です。

次に自然に「わく」バクテリアが通性嫌気性細菌の中で都合の良い細菌メインの場合は、
アクア業界で一般に知られる分解の流れとは違います。
以前にも書きましたが タンパク質→アミノ酸→アンモニア→亜硝酸→硝酸塩 というのは酸化細菌メインのお話です。
都合の良い通性嫌気性細菌メインの場合は タンパク質→アミノ酸→栄養源として吸収。リン酸は細胞分裂時の染色体の材料として吸収。
という訳で増える物はあまり増えず、KHも消費されないのでPHも下がりません。でもミネラルは減少傾向にありますから補給は必要です。
更に、細胞分裂を何回かして死んでしまったバクテリアの死骸(低床や濾過槽にたまるヘドロ状の物)を分解できる種類の通性嫌気性細菌の場合はいいとして、そうでない場合はフィルターの掃除が必要になります。
掃除の時に洗い過ぎると、今まで生命維持に貢献してきたバクテリアのほとんどが流されてしまう為、飼育水でほどほど洗い、あまり綺麗にしないまま終わりにする。
水はあまり換えずフィルターをほどほど掃除するという方法。
かなりおおまかですが、この2つの方法が昔からの一般的な水槽管理の方法です。
・・・・・思いのほか長くなってしまいました、続きはまた今度
レッドビーシュリンプ飼育用品のYahoo!ショッピングやレッドビーシュリンプのヤフオク!もご覧ください。

にほんブログ村
ここからは状況によって枝分かれします。
それは地域によって水換えに使う「水」そのものが違うからです。
それと、自然に「わく」バクテリアの種類とバランスも違うからです。
例えば当店(富士市蓼原)の水道水の「水」は日によってバラつきはありますが、
リン酸値1リットル当たり1.0~2.0mg、硝酸値1リットル当たり30~40mg
ついでに珪酸値1リットル当たり10~50mg以上(多すぎて計測不可能な日もありました)
それなのにPHは8.0~8.5
余談ですが、この3種類はそれぞれ、緑ゴケ、黒ひげゴケ、茶ゴケの主栄養素です。
これらを減らしたいのに水を換えれば換えるほどコケは元気になってしまいます。

このような富士市の水は矛盾以前の問題ですが、水替えに使う水にリン酸、硝酸が無いという事が前提で、部分換水をしている場合は
徐々に水換えの量を増やしたり、水換えの周期を早めたりします。それでも常に悪化していく為、定期的な全換水をする必要があり、(ほぼリセット状態)
その全換水までの時間稼ぎの手段として普段の部分換水がある訳です。
フィルターはなるべく洗わず、とにかく水換えという方法。
この考えは、自然に「わく」バクテリアが硝酸に変化させる好気性の酸化細菌メインの場合です。

次に自然に「わく」バクテリアが通性嫌気性細菌の中で都合の良い細菌メインの場合は、
アクア業界で一般に知られる分解の流れとは違います。
以前にも書きましたが タンパク質→アミノ酸→アンモニア→亜硝酸→硝酸塩 というのは酸化細菌メインのお話です。
都合の良い通性嫌気性細菌メインの場合は タンパク質→アミノ酸→栄養源として吸収。リン酸は細胞分裂時の染色体の材料として吸収。
という訳で増える物はあまり増えず、KHも消費されないのでPHも下がりません。でもミネラルは減少傾向にありますから補給は必要です。
更に、細胞分裂を何回かして死んでしまったバクテリアの死骸(低床や濾過槽にたまるヘドロ状の物)を分解できる種類の通性嫌気性細菌の場合はいいとして、そうでない場合はフィルターの掃除が必要になります。
掃除の時に洗い過ぎると、今まで生命維持に貢献してきたバクテリアのほとんどが流されてしまう為、飼育水でほどほど洗い、あまり綺麗にしないまま終わりにする。
水はあまり換えずフィルターをほどほど掃除するという方法。
かなりおおまかですが、この2つの方法が昔からの一般的な水槽管理の方法です。
・・・・・思いのほか長くなってしまいました、続きはまた今度
レッドビーシュリンプ飼育用品のYahoo!ショッピングやレッドビーシュリンプのヤフオク!もご覧ください。

にほんブログ村




















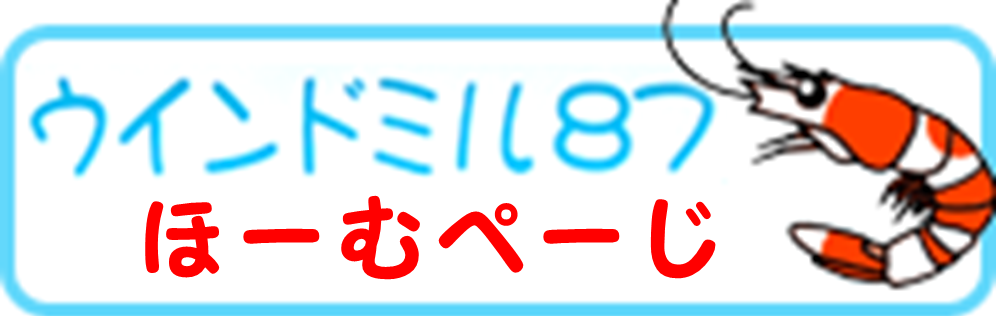
 オークションはこちら
オークションはこちら















